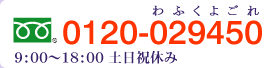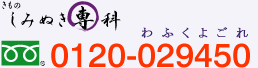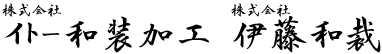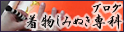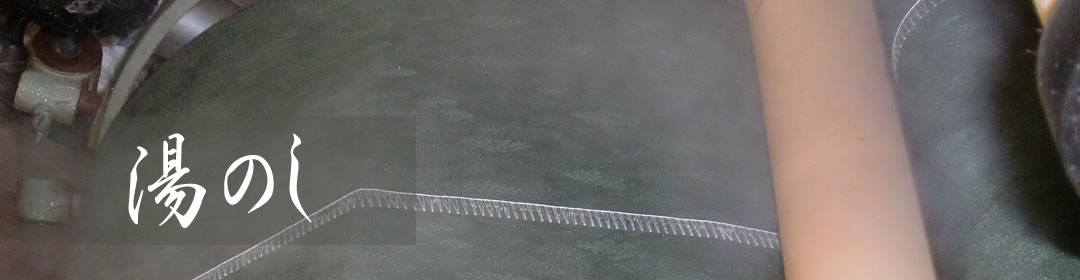
湯のし
仕立ての良し悪しを左右する大事な工程です。
湯のしとは、反物に蒸気をあてて生地を柔軟にするのと同時に、シワを伸ばし、縦糸と横糸の繊維を均等にし、幅を整える作業のことで、 洗い張りの仕上げ、ガード加工の前、仕立ての前に行われる工程です。見過ごされがちな工程ですが、着物の仕立てをする前の大変重要な工程で、湯のしをしっかりやっておかないと、 あとの仕立て上りに大きく影響します。仕立ての良し悪しはこの湯のしによって変わってきます。
湯のし 工程紹介
湯のし 工程
仕立てる前のまだ、裁断していない状態の時(丸巻きの反物)に湯のし加工をすることを言います。
 1.高温の蒸気をかけているところです。
1.高温の蒸気をかけているところです。 2.縦糸と横糸の繊維を均等にし、幅を整える作業をしています。
2.縦糸と横糸の繊維を均等にし、幅を整える作業をしています。
解き湯のし 工程
仮縫いの着物を一度解いて(丸巻きの反物の状態にしてから)、湯のし加工をすることを言います。
 1.湯のし機を動かします。
1.湯のし機を動かします。 2.生地に縦の折スジがあります。
2.生地に縦の折スジがあります。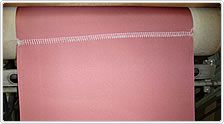 3.湯のし機で縦の折スジを消しました。
3.湯のし機で縦の折スジを消しました。
湯のし巾だし 工程
湯のし機で何度も何度も湯のしをして布巾を少しずつ広げる方法です。紹介例は総絞りの絵羽柄の羽織りの巾出しです。
 1.仮絵羽の状態の総絞りの羽織です。この羽織りを巾出しします。
1.仮絵羽の状態の総絞りの羽織です。この羽織りを巾出しします。 2.一回目の巾出しの工程です。少しずつ布巾を広げていきます。
2.一回目の巾出しの工程です。少しずつ布巾を広げていきます。 3.3回目の巾出しの工程です。高温の蒸気を生地に吹きかけています。
3.3回目の巾出しの工程です。高温の蒸気を生地に吹きかけています。 4.今回は5回目の巾出しの工程で出来上がりました。これぐらいの巾で本仕立てが出来ると思います。
4.今回は5回目の巾出しの工程で出来上がりました。これぐらいの巾で本仕立てが出来ると思います。 5.巾出しの仕上がりです。た。これぐらいの巾で本仕立てが出来ると思います。
5.巾出しの仕上がりです。た。これぐらいの巾で本仕立てが出来ると思います。
湯のし 事例
事例1.初着の湯のし
男の子のお宮参りの初着を湯のししました。伊藤和裁でこの着物を羽織に仕立て直す為です。既製品のミシンで仕立てありましたので、縫い針の穴やプレス機でついたスジを取るために湯のしの蒸気を生地に十分に当て、機械が動くスピードを遅めに丁寧にして直しています。
事例2.黒留袖の下のし
仕立て上がっていた黒留袖を全て解いて、羽縫いをして湯のしをしています。着物に大変キツイ筋が縦についているのが分かると思います。今回の湯のしは下のしいい、洗い張りをする前にする湯のしです。生地のズジやシワを伸ばし、シミや汚れを見つけやすく、生地を整理して作業をしやすくする意味があります。
湯のし 料金
クリーニング・加工料金や仕立て、仕立て直し等、ご依頼料金の
合計金額が\38,500(税込)以上の場合は送料は弊社負担とさせていただきます。
合計金額が\38,500(税込)未満の場合は送料はお客様負担となります。
(見積のみやキャンセルの場合も送料はお客様負担となります)
☆出来上がり連絡後、1カ月以内に出来上がり品をお引き取り頂けない場合、ヤケやシワ他等、保管に関する責任は負いかねます。
| 湯通し料金(税込) | |
|---|---|
| 湯のし | 3,300円 |
| 解き湯のし | 6,600円 |
| 湯通し | 6,600円 |
| アンサンブル 湯通し | 13,200円 |
| 水通し | 5,500円 |
| 藍止め | 5,500円 |
| 巾出し湯のし | 5,500円 |
| 浴衣藍止め | 4,400円 |
| 浴衣巾出し湯のし | 4,400円 |
| 本ふかし | 11,000円 |
| 仕立て上がり浴衣藍止め | 8,800円 |